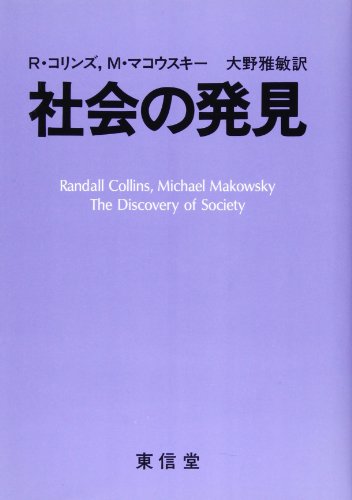原題:The Discovery of Society. 3rd ed (1984)
著者:Randall Collins(1941-) 社会学。
著者:Michael Makowsky 社会学。組織コンサルタント。
訳者:大野 雅敏[おおの・まさとし](1927-) 社会学。
【目次】
序文 [ii-iii]
訳者まえがき(一九八七年八月 大野雅敏) [iv-ix]
目次 [x-xiii]
凡例 [xiv]
序論:社会と幻想 003
幻想の源泉 005
社会学の貢献 017
社会学の境界 020
第一部 一九世紀合理主義の推移
1 パリの予言者たち:サン=シモンとコント 024
アンリ・ド・サン=シモン 026
オーギュスト・コント 032
2 アングラ社会学:カール・マルクス 038
マルクスの生涯 040
マルクスの社会学 043
階級と階級意識
マルクスの政治理論 046
マルクスの経済学 050
労働価値説/搾取としての利潤/利潤率低落の法則/周期的な恐慌/資本主義の最終的崩壊
マルクスの社会・政治哲学 055
マルクスの遺産 059
エンゲルスの性差別階層論 060
3 最後の紳士:アレクシス・ド・トクヴィル 067
アメリカにおける平等 070
政治機構/地理的・歴史的偶然性/アメリカ文化
4 ニーチェの狂気 083
ニーチェの生涯 084
人類学の誕生と不合理の発見 087
キリスト教への攻撃 089
意志の力学 092
一切価値の再評価 095
ニーチェの狂気 097
一つの評価 100
5 社会改良家、進化理論者、人種差別主義者 103
ファーガソンとスミスの道徳哲学 104
自由主義と社会改革:ベンサム、マルサス、ミル 105
社会進化論:ダーウィンとスペンサー 108
アメリカにおける自由主義 112
科学の限界 118
社会生物学の復活 120
ダーウィンの帰結 124
第二部 大規模な飛躍
6 ドレフュスの世界:エミール・デュルケムとジョルジュ・ソレル 126
デュルケム:社会における分業 128
逸脱行動と社会的連帯/宗教と現実
ジョルジュ・ソレルの革命哲学 142
7 魔術的世界の解放:マックス・ウェーバー 145
ウェーバーの社会学:階層・組織・政治 149
階層:階級・権力・身分/組織:家産制度と官僚制度/政治:伝統的・カリスマ的・合理・合法的正当性
ウェーバーの歴史理論:世界の合理化 162
8 非合理の征服者:ジクムント・フロイト 172
初期の人生および業績 173
夢の解釈/抑圧
フロイトの説明体系 179
一次・二次過程/性的発達段階説/リビドー説/自我・イド・超自我/エロス対死の本能
晩年 186
フロイト学派の動向:アドラーとユング 187
集合的無意識
フロイトの遺言 193
的著書棚批判と前進 195
フロイトは性差別論者 198
9 見えぬ世界の発見:ジンメル、クーリー、ミード 203
ジンメル 203
クーリーの生涯と業績 207
クーリーの体系 209
鏡の自我と第一次集団
クーリー批判 214
ミードの生涯と業績 216
ミードの体系 217
社会的自我/一般的他者
ミード批判と評価 224
第三部 二〇世紀諸理論の変遷
10 日常的世界の発見:トマス、パーク、シカゴ学派 228
トマスの生涯と業績 229
パークとシカゴ学派 231
シカゴ以外の経験的諸研究 234
組織の社会学 237
11 社会体系の構築:パレート、パーソンズ 240
パレートの生涯と業績 241
パレートの体系 243
パレート批判 245
パーソンズの生涯と業績 246
パーソンズの社会理論 249
一体系としての社会/機能主義/社会統合/社会変動
パーソンズの宗教社会学 255
パーソンズの貢献 257
12 ヒトラーの幻影:ミヘルス、マンハイム、ミルズ 260
ミヘルスの寡頭制に関する鉄則 262
マンハイムの社会相対主義理論 267
マンハイムの近代社会のための政治学 273
マンハイム理論の現代的適用 278
13 社会的出会いの劇場:アーヴィング・ゴフマン 282
ラベリング理論 283
ゴフマンの社会生活に関する劇場モデル 286
エスノメソドロジスト 290
ゴフマンの機能的必然の概念 293
哲学の帝国主義 295
微視社会学の影響 297
終論:過去と未来の社会学 299
社会学の発展 303
将来の予測 310
引用・参考文献 [315-333]
人名索引 [334-341]
事項索引 [342-350]
【メモランダム】
・Amazon.comには、訳者も知らなかった、もうひとりの著者の略歴が載っている。
Michael Makowsky is organizational consultant to Musart Company. He earned his B.A from New York University's Washington Square College in 1962, and received his M.A. in Sociology from the University of California at Berkley in 1967. Over the last 30 years, he has taught at his alma mater, the University of California at Berkley, as well as the University of California at Davis, Chabot College, College of San Mateo, Goddard College, the California Institute of Integral Studies, and the Cultural Integration Fellowship. He is the author of numerous articles in contemporary journals, such as Minstrel of Love: A Biography of Satguru Sant Keshavadas, Breath of the Eternal: The Way of Self-Knowledge: The Concept of Atman in Four Upanishads. He is the president of his own company, Deal Glamour Media and Education Productions and is a member of the Dr. Martin Luther King, Jr. Committee of Las Vegas.
【抜き書き】
□「訳者まえがき」
・まず、翻訳に関する但し書き、著者の略歴、本書の性格、本書の構成、別の著作との関連性などについて。本書が絶版なのでやや長めに抜き書きする。
訳者まえがき
本書はR・コリンズとM・マコウスキー著『社会の発見』(Randall Collins and Michael Makowsky, 1984, The Discovery of Society. 3rd edition.)三版の全訳である。しかし、逐語訳ではない。市販に耐えるために、内容の意味を失わず全体的にやや分量を短縮したからである。原著者の承認を得て、わが国の読者に不案内な例証を削減もしくは削除し、繁雑な表現を簡明に改める作業を行った。ただし、分節全体を省略した個所は一つもない。要するに、全体的に内容と表現を凝縮し、邦文としての読みやすさに留意したものである。
主要な原著者コリンズには一九八三年にサンディエゴ所在の彼の自宅で会い、翌八四年に彼の問題の書『資格社会――教育と階層の歴史社会学』(一九七九)の訳稿をすでに刊行した(東信堂・一九八四)。その「訳者あとがき」に詳しく彼の経歴・業績・解説を述べたので、ここでは簡略な紹介に止める。(なお共著者マコウスキーに関しては、原書になんの記述もなく、訳者も寡聞にして知らず、コリンズに問い合わせるより他に調べる術もない。)
コリンズは一九四一年生まれ、一九六三年ハーバード大学(文学士)、翌年スタンフォード大学(修士・心理学)、一九六九年カリフォルニア大学・バークレー校(博士・社会学)の学歴をもつ。その後に変更がなければ、現在も南カリフォルニア大学客員教授のはずである。〔……〕彼の立場は新ウェーバー学派といわれ、一言にしていえば巨視的・微視的の両観点を統合し、階層を核とした一般化理論の構築を試みる。その業績により、一九八三年にはアメリカ社会学会の理論賞を得ている。
本書の初版は一九七二年における彼の処女出版であり、再版は七八年、そして本書の三版へと続き内容的に加筆・増量されている(八三年に改訂された痕跡は、6章の“宗教と現実”にある)。本書は彼の学問背景を反映して、広範な基盤で社会の発見者をたどる。内容は序論・終論に加えて三部・二一章に分かれ、サン=シモンからゴフマンに及ぶ。目次に現われた思想家は二九名であるが、本文中に記載の人名は実に一七〇名にのぼり、社会学を中心としながらも、社会思想史に関係する限りの経済学・人類学・政治学・心理学・歴史学、さらに哲学・言語学・生物学・数学等の諾分野における人物や、それに映画俳優までが登場する。
しかも、コリンズの立場から思想史の流れに沿って、各人物が統一的に把握されている点が特徴である。個別的な思想家に関する参考・解説書は容易に見出されるが、この総合的で要領を得た記述が本書の三版を重ねた秘密であろう。このように広範にして適切な社会学に関する、いや人間探究に関する教養書はなかなか発見し難い。本書中にコリンズもいうように、「全面的に一般化理論を促す唯一の学術環境は、学生への教科書執筆の必要性だが、これも研究統合の意図よりも、全くの異質領域での研究要約に傾く」(終論“将来の予測”)状況にある。以上の観点から見ると、本書は初学者のための単なる教養書の域を超えているともいえよう。
その上、コリンズ研究者にはいうまでもなく、少なくとも『資格社会』の読者には、これはコリンズの理論的根拠を示して示唆に富む。その後に理論賞を獲得した研究者が弱冠三一歳の時点で著わした本書は、その理論的諸要素をどこから得て自らの理論を構築したのか、まさにその謎解きを与える。
コリンズは基本的にウェーバー(7章)の分析的解釈にマルクス(2章)、デュルケム(6章)、ゴフマン(13章)の関連諸原理を組み込みながら階層化理論の説明を試みるので、それら思想家の描写部分はいうまでもない。その他、例えば『資格社会』における、(1)自己規制集団としての専門職業の愛他主義の本質暴露は、ニーチェの「道徳意識と愛他主義(が)権力に圧迫された意志の迂回的所産であり、機会の到来と共に支配の道具となる」(4章“意志の力学”)が基盤にある。(2)合衆国の近代史を描いた部分では、トクヴィルの地理的要因の強調(3章“地理的・歴史的偶然性”)や、地方分権制がイギリスの封建統制に起源をもつ(同“アメリカ文化”)との指摘を用いる。(3)定型的文化生産機関としての学校と並ぶ職業芸能人については、クーリーの社会心理学(9章“鏡の自我と第一次集団”)でのスター制度が対応する。(4)また、『資格社会』における組織研究の記述は、まさに本書のウェーバーからミヘルス(12章)やマンハイム(同)のそれと全く類似する。
各章の終わりには各思想家に対するコリンズ自身の評価があり、彼の観点理解を助けると共に、特に序論と終論とは彼の統一的な理論的観点を要約するものである。すなわち、社会的事実発見の困難性、一連の先行業績の流れに関する要約へ事実と価値との峻別、純粋な一般理論の応用的側面としての価値の問題、個人的自由の極大化と被抑圧者(女性・少数民族・貧者)の側への価値体系の傾斜、社会的思考形式決定の社会的原因を明確にする知識社会学の要請、そのためにも純粋な一般化的説明理論への巨視・微視両観点の統合・発展の希求、ある政治権力集団の計画化に奉仕する実際的ノウハウ知識情報の戒め、真に自由な知識人への期待、増大する核の脅威に対する警告等々である。
・ここから唐突に脱線して、「教育制度」云々。
ここで、訳者の問題関心である教育制度について本文中のコリンズに語らせ、彼の応用面に接近した観点の要約を試たい。概略の粗い形で十分ではないと思うが、詳細は本文によって補って欲しい。原著者の思いが必ずや共感を呼ぶに相違ない。
かつて「福祉国家アメリカにおける大学関係の自由主義的提案者でも、……社会事業と公教育を万能薬とする信念以上のものをほとんど示してはこなかった」(序論“社会学の貢献”)。そして今日、教育制度は「巨大な青少年人口を擁するまで拡大してきたが、……万人に上昇移動の機会を与える代わりに、雇用の教育要件を引き上げ、かつて初等学校脱落者のものであった低級職を、高校卒業者が求めるように作用する。そして、巨大な官僚制度がなお拡大するに伴い、競争的な社会階層制の底辺に存する不従順と疎外とが、学校制度のなかにも移行する。……いまや学校制度が(社会)それ自体の問題の器とも原因ともなっている」(5章“アメリカにおける自由主義”)。
もうわれわれは、内外の教育制度に関する情報の切り売りや、戦後教育制度の原理・原則の繰り返しを超えなくてはならない。とはいえ、そのために依拠すべき確実な価値・真理はあるのか。古典的な比較教育学で行われた「機会の拡大」は、もう基準とはなり得ない。ここでわれわれは、マンハイムが直面した深刻な相対主義の脅威に当面する。
マンハイムの回答は、五つの政治思想(官僚制的保守主義、伝統的もしくは歴史的保守主義、ブルジョワジー的保守主義、社会主義、ファシズム)のうち、少なくともいま現実に存する世界に実現可能な超歴史的な官僚制のなかで、実質的合理性を求める聡明な計画化である。「それにはまず.……教育制度を、盲目的な自己膨張・強大化のまま放置せず、統制することに向けられなければならない」のである(12章“マンハイム理論の現代的適用”)。(コリンズは『資格社会』で、文化の集約的表現としての「資格」「証書」のインフレ状況を詳説している。)
そして「必然的に近代産業社会は、エリートに運営される有力な集権的官僚制で成立する」が、「自由主義イデオロギーで非合理性を隠した盲目的・無責任なエリートに統制される」のではなく、「社会科学に訓練された新エリート」(12章“マンハイムの近代社会のための政治学”)によるものでなければならない。すなわち、マンハイムが近代社会に準備した三選択肢のうち(組織の機能的合理性に関する盲目的無計画性、ファシスト専制の非合理性、理知的で人間性豊かなエリートによる計画化)、前二者を排除するものである。
それには、まずわれわれの有する第一の幻想を打破する必要がある。これまで教育制度は、あたかも客観的実在物であるかのどとく主に外側から扱われた。しかし、組織・制度・社会といい、人間は「自ら創るか創るらしきもののなかでの存在として束縛されてはいるが、それでもなお社会的世界は人間自身の所産」なのである。社会学の進展に伴い、いまや「確実で強固と思われた世界は、可能性の宇宙に解放されて瓦解する」(13章“微視社会学の影響”)。それ故に、例えば「社会の競争適合性により貧者(もしくは人間)を判断せず、社会を彼らに(もしくは制度を被抑圧者に)適合させることも可能である。……重要な問題は普遍的な人間の権利に無頓着で、社会上位者の特権をそのまま留保する形態に加担するかどうか」(5章“科学の限界”)なのである。
われわれは「自分の常識的実際界に住み、善・悪と世俗・神聖の区別を各個人に伝える社会的儀式に包まれている。……多数の主観的世界に人は住み得る」し、「/i>その世界は個人にとりなんら客観的真理をもつ必要はない。……個人は暗黒の歪曲や完全な神秘のなかにも住み得るし、また住んでいる」(終論)。しかし、少なくとも知識のための知識探究が支持を得る知識専門家集団においては、経験的資料の蓄積や技術的洗練にのみ従事する者、それに特定の「政治的イデオローグは、地位階層の力学と官僚制組織の統制不能な惰性力に関するウェーバーの真理や、非人格的規則と没感情的組織の世界における個人的緊張に関するデュルケムやフロイトの発見を、いまなお認めねばならない」(序論“社会学の貢献”)であろう。
諸科学の変動期における学際的研究が唱導されるこの時期に、狭い専門領域の壁を守るのは無意味であると訳者は考える。第一に、いかなる学問領域といえども、必ずその基盤には他学と共通する有力なパラダイムを有する(拙著『教育制度変革の理論』〔東信堂・一九八四〕を参照されたい)。第二に、原著者による教育関係著書『資格社会』は、副題は「教育と階層の歴史社会学」であるが、ウェーバーの経済・政治・文化の三要素を方法論的支柱とする、高等教育制度発展のアメリカ・イギリス・フランス三国に関する比較研究である。第三に、訳者の勤務大学の講座編制上、このような広範な観点から新しい教育研究の方向を生むことが期待されているのである。
・謝辞など。
本書は最初、難解なコリンズの『資格社会』理解のために学生と読み始め、邦訳原稿が完成したものである。その後の作業過程は次のとおり。(1)邦訳原稿では約二〇%(原文では一〇%程度)を凝縮し、院生の門脇勝治、近藤誠両君の検討を経た。(2)初校ゲラの段階での推敲は、専門用語の検討と同時に、許される範囲内において過度に及ぶ短縮部分の復活にあった。ここでは特に、訳者の勤務大学スタッフの藺千壽・勝倉孝治両氏に心理学関係の訳語と、鈴木敏紀氏には経済学関係の訳語について示唆を得た。(3)最後に、訳稿全体の総合的検討に当たり、同じくスタッフの西穰司・若井彌一両氏による貴重な時間を割いてのご協力を得た。以上の諸君。諸氏に厚くお礼を申し上げたい。
その他、人名や参考邦訳文献について多くの方々から得たご援助や、院生諸君による人名・事項索引の照合作業、それにこの訳書の出版にご理解をいただいた東信堂の下田勝司氏と、極度の短縮部分の復活を含む校正作業に従事された二宮義隆氏の皆さんに感謝申し上げたい。
さらに加えれば、この広範な領域に及ぶ訳出作業には、万全を期したつもりでも思わぬ誤りがあるかもしれない。分量短縮のための取捨選択や表現の簡潔化を含めて、その責任はいうまでもなく訳者が負う。大方のご叱正とご教示を賜れば幸いである。
・社会学、経済学、哲学について短いまとめ。(蛇足だが、この部分については、松尾匡(2009)『対話でわかる痛快明解 経済学史』の、「第3章 マルクス」の記述もあわせて方も読んでほしい。各思想家を四象限を使って解説する試みが奏功しており抜群に分かりやすい。)
pp.42-43
マルクス生涯の業績は総合的な一体系を成すが、分析目的のためには次の三部門に分けられよう。①階級意識と階級闘争の分析をめぐり構築された社会学、②資本主義の内部矛盾を展開する経済学、③疎外の概念と共産主義での解決を扱う社会・政治哲学である。その社会学は基本的に正しいことが判明し、その後の理論発展に重要なものとなってきた。彼の経済学は、ある重要な問題は提起するが決定的な欠陥をもつ。彼の哲学は、結局それを個人が天啓の源泉として受容もできるし拒否もできる価値前提と、世界認識の方法に基づいている。要するに、マルクスの全体系を受容せずに、彼から多くを学ぶことが可能なのである。
・社会生物学。
(p.120)
一九世紀思想家の悪評にもかかわらず、生物学的社会学が近年に復活した。主な提唱者は生物学者であるが、社会学にも追従者も得ている。〔……〕エドワード・O・ウィルソンは、新領域である社会生物学の創始者であり、それは「あらゆる社会行動の生物学的根拠に関する体系的な研究」と定義される。
社会学での古い自然・対・養育の問題は、伝統的に養育に有利であったが、ウィルソンにより逆転された。
(p.122)
「社会ダーウィン主義」と人類の社会組織の複雑性を頂点とする点で、ウィルソンはH・スペンサーやW・G・サムナーと理論上同類である。人類社会自体は集団規模・遺伝子交換率と、各成員の行動・業績での不平等による階層的資産の点で、非人類社会以上に異なる。〔……〕彼の観察では、この「生態学的解放」(ecological release)で人類は過去一万年の環境支配に成功し、文化の一貫性と再生産を維持してきた。しかし、人間の愛他主義にもかかわらず、科学革命の主な政治的帰結として、〔……〕殺戮手段過剰保有により、しだいに高まる大量殺害と種族絶滅の危険可能性の説明を、ウィルソンは欠落させている。
彼の社会生物学は、政治的には反動と見られてきた。多数の社会生物学者は性の役割に関して保守的結論を導き、女権論者により強く攻撃された。ウィルソンと同僚ラムスデンは、文化的相違に関する生物学的根拠で、旧式な人種分離主義に接近するに至る。